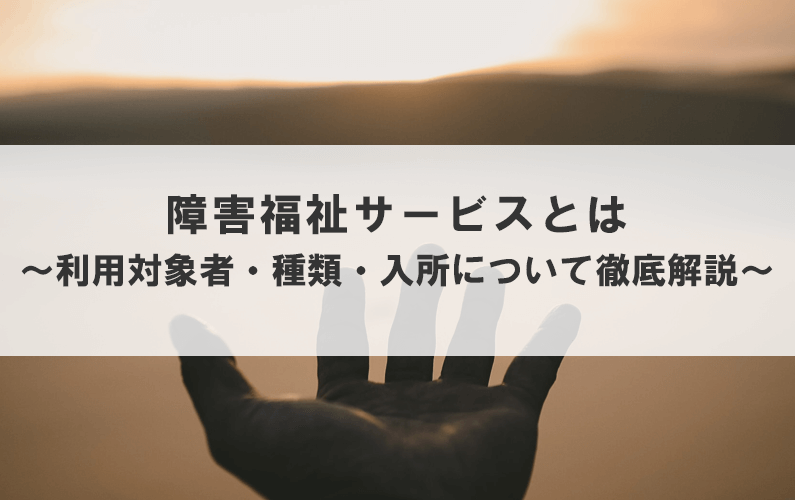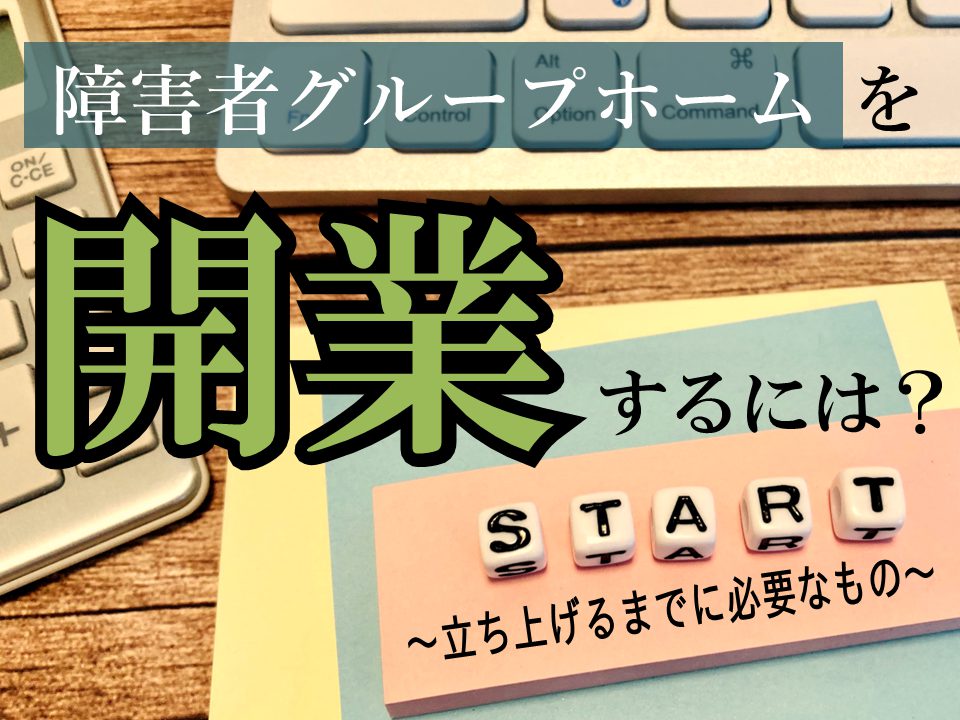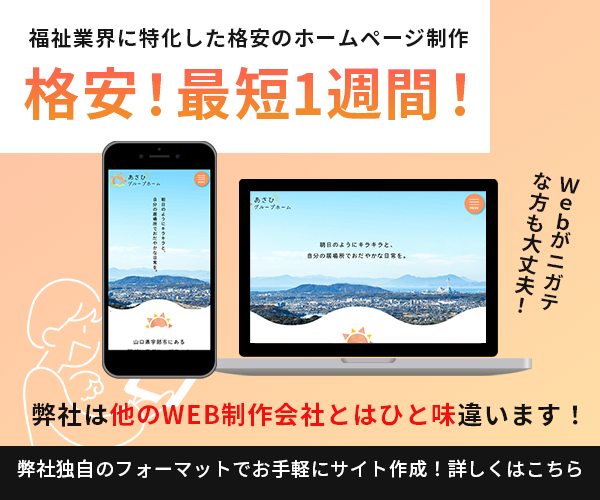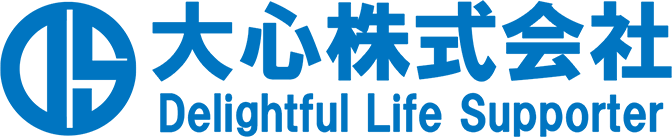就労継続支援B型事業所を開業するには?指定申請や開業の流れを解説します!
2025.01.23 #就労継続支援B型#経営について#障がい福祉について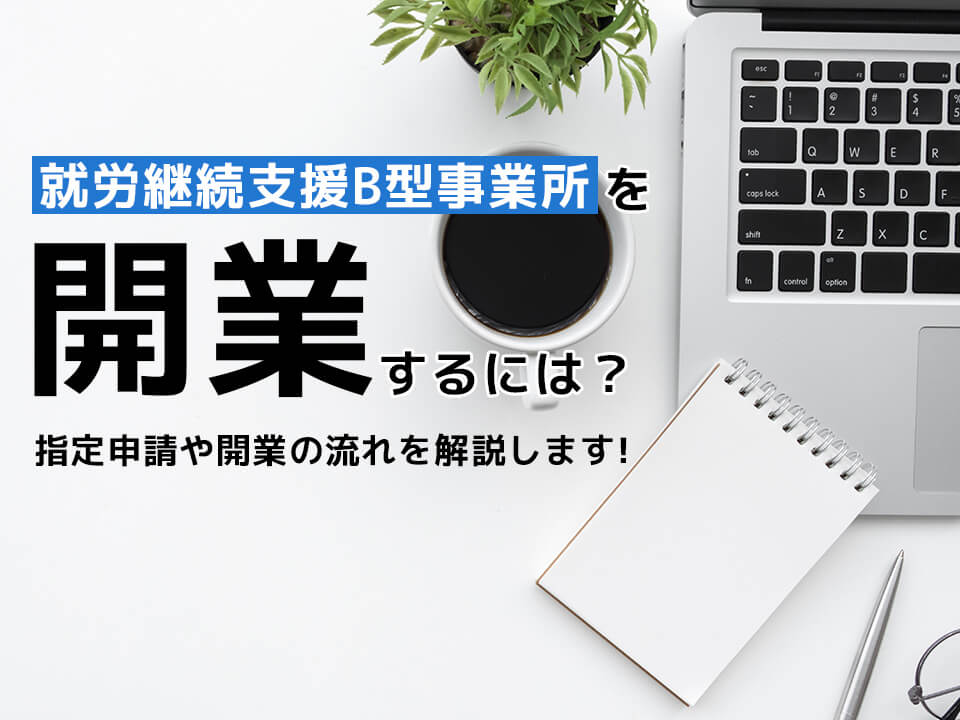
就労継続支援B型事業所の開業までには、さまざまな手続きや準備が必要です。
本記事では、指定申請の流れや開業までの具体的なステップについて詳しく解説します。
この記事の目次
就労継続支援B型事業所の基礎知識
就労継続支援B型事業所とは?
就労継続支援B型事業所は、障がいや難病が理由で一般就労が困難な方に対し、生産活動や社会参加の機会や訓練の場を提供する福祉サービスです。
就労継続支援B型事業所では、利用者が「生産活動」と呼ばれる業務に携わることで、働くスキルの維持向上や社会参加を目指します。
この生産活動の成果として、利用者には「工賃」が支払われます。
また、事業所は生産活動に加えて、仕事や生活に関する相談対応、ビジネスマナー研修、さらにはA型事業所や一般企業への就職支援など、幅広いサポートを提供します。
必要に応じて、行政や医療機関、福祉関連機関、企業との連携を図りながら、利用者一人ひとりに適した支援を行います。
就労継続支援B型事業で利益を増やすには?
福祉サービスで利益を追求することに対して、否定的なイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、事業所が安定した利益を確保できなければ、運営の継続はもちろん、利用者への支援の充実や事業の発展も難しくなります。
利益を確保することで、より多くの利用者を受け入れることが可能となり、新たな障害福祉サービスの展開にもつながります。
その結果、支援の幅が広がり、より多くの方々に就労機会を提供することができるのです。
就労継続支援B型事業所の運営においては、利用者のニーズに応えることはもちろん、事業を安定して継続させるためにも、利益を上げることが重要な要素となります。サービスの質を向上させ、より良い支援を提供するためには、利益を出していくことを考えなければいけません。
就労継続支援B型事業所の主な収入源は下記の2つです。
1.障害福祉サービスの報酬
就労継続支援B型事業所は、利用者と契約を結び、サービスを提供することで障害福祉サービスの報酬を受け取ります。
報酬の大部分は「訓練等給付費(給付金)」として、国民健康保険団体連合会(以下、国保連)を通じて市町村から支払われます。ただし、利用者の前年の収入に応じて、一部自己負担が発生する場合があります。
事業所が受け取る報酬は、大きく「基本報酬」と「加算」に分かれます。基本報酬は収入の柱となるもので、B型事業所では利用者1人あたり、1日ごとのサービス提供に応じて支給されます。
一方、加算は特定の条件を満たした場合に、基本報酬に上乗せされる形で支給されます。
また、事業所が指定基準を満たしていない場合には、「減算」が適用され、受け取れる報酬が減額されることがあります。
減算は経営に大きな影響を及ぼすため、基準を遵守し、適切な運営を行うことが重要です。
2.生産活動による売上
事業所の生産活動による収入は、会計上「就労支援事業収入」として分類され、障害福祉サービスの報酬とは区別して管理する必要があります。
この収入から経費を差し引いた利益は、原則としてすべて利用者への工賃として支払われ、事業所の利益として残すことはできません。
しかし、工賃の安定的な支払いを維持したり、将来的な設備投資に備えたりするための積立については、一定の要件を満たすことで認められる場合があります。
●主な支出項目●
開業後にかかる支出には、以下のようなものがあります。
- 事業所職員の人件費
- 事業所の賃借料
- 水道光熱費
- 消耗品費
- 通信費
- 教材費
- サービス利用者の工賃
- 生産活動にかかる経費
注意すべきポイントとして、主な支出項目のひとつである「工賃」は、国からの報酬ではなく、就労継続支援B型事業などで生産活動をした利用者に支払う対価のことです。
就労継続支援B型を開業する際に必要な資金とは?
就労継続支援B型事業所を開業するには、「開業資金」と「運転資金」の2種類の資金が必要です。
開業資金は事業所の準備にかかる初期費用を指し、運転資金は開業後に報酬が支払われるまでの運営費用を指します。
事業の立ち上げ時には、予想外の支出が発生する可能性もあるため、どちらの資金も余裕をもって計画を立てることが重要です。
十分な資金を確保することで、スムーズな運営を実現できるでしょう。
開業資金
就労継続支援B型の開業までには、以下のような費用が発生します。 また、開業までに必要な資金は300万円から500万円前後と考えられます。
- 法人設立費
- 物件取得費
- 人材採用費
- 事務用品購入費
- 設備導入費など
運転資金
運転資金(ランニングコスト)は、以下の支出によって毎月150~170万円前後がかかります。
- 物件の工賃
- スタッフや利用者の人件費
- 消耗品費
- 光熱費など
開業後の初期段階では、最低でも2か月間は赤字が続くことを想定し、資金計画を立てることが重要です。
訓練等給付費が支払われるタイミングを考慮し、十分な運転資金を確保しておきましょう。
事業を安定して運営するためには、最低でも3〜6か月分のランニングコストを見込む必要があります。
B型事業所を開業するには?
開業後に指定基準を満たせなくなると、給付費の減額や行政指導を受ける可能性があり、最悪の場合は指定を取り消されることもあります。
そのため、指定基準を十分に理解することが大切です。
1.人員基準
職員配置基準を満たす必要があります。サービス管理責任者や職業指導員など、役割ごとに必要な資格や経験が求められます。
人員配置基準
就労継続支援B型事業所の人員基準に定められている職種は下の3つです。
- 管理者
- サービス管理責任者
- 生活支援員・職業指導員
職業指導員と生活支援員の人員基準は、「前年度の平均利用者数を10で割った数(10:1以上)」以上の配置が必要です。
ただし、「6で割った数(6:1以上)」または「7.5で割った数(7.5:1以上)」の人数を配置し、指定権者に届け出ることで、より高い報酬区分が適用されます。
そのため、多くの事業所では基準を上回る人数を配置しています。
管理者
常勤で1人以上の配置が必須です。 事務所の従業員や業務の統括管理、その他の管理業務を一元的に担います。管理業務に支障がない範囲で、他の職務を兼務することも可能です。
サービス管理責任者
サービス利用者への支援を総合的に管理するほか、個別支援計画の作成や、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理などを行います。
利用者が60人以下の場合は、常勤で1名以上の配置が必要となり、61人以上の場合には40:1の割合で人員を追加する必要があります。
生活支援員・職業指導員
職業指導員は、障がいのある方が能力を最大限に発揮できるよう、実際に仕事を共に行いながら技術指導やサポートを行います。
一方、生活支援員は、日常生活のサポートや創作・生産活動の支援を通じて、障がいのある方の自立を身近な場面で支えます。
2.設備基準
就労継続支援B型事業所の「設備基準」は、利用者が安全かつ快適に過ごせるように定められた規則です。
この基準は、利用者の障がい特性への配慮や安全性、プライバシーの確保などの観点から設けられています。
設備基準の内容は厚生労働省が定めるものが基本となりますが、自治体によって独自の要件が追加される場合があります。
そのため、事前に管轄の行政機関へ確認し、基準を満たした設備の準備を進めることが重要です。
| 設備 | 基準 |
| 訓練・作業室 | ・訓練や作業に支障のない広さがある ・訓練や作業に必要な機械器具・備品などを揃える ※支援に支障がなければ設けないこともできる |
| 相談室 | ・話し声が漏れないようにプライバシーに配慮し、間仕切りなどを設ける |
| 洗面所 | ・利用者の特性に応じたもの |
| トイレ | ・利用者の特性に応じたもの |
| 多目的室 | ・支援に支障がなければ相談室との兼用もできる |
3.法人格の取得
就労継続支援B型事業を運営するには、法人格を取得することが必須です。
具体的には、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人などの法人形態が該当します。
すでに法人を持っている場合でも、定款の「事業目的」欄に障害福祉サービスに関する記載がない場合は、法務局で目的変更登記を行う必要があります。
法人形態の選択は事業の目的や運営方針に応じて異なります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、慎重に比較検討しましょう。
例えば、NPO法人は社会的信頼性が高い一方で、金融機関からの融資を受けにくい傾向があります。資金調達を視野に入れる場合は、他の法人形態の選択も考慮する必要があるでしょう。
4.運営基準
「運営基準」とは、事業所が提供すべきサービスの内容や、利用者への説明事項、必要な書類の掲示や記録・保管方法などについて定めた基準です。
事業所運営の指針となるものであり、スムーズな開業と適正な運営のために、早めに内容を把握し準備を進めることが重要です。
また、運営の方針やサービス利用に関する具体的なルールを明確にするために、「運営規定」を作成しなければなりません。これには、事業所の運営方針や利用者がサービスを受ける際の留意事項などが含まれます。
5.消防法上の要件
事業所として使用する物件が消防法の基準を満たしているかどうか、事前に管轄の消防署(予防課)に確認する必要があります。
消防法は非常に専門性が高く、物件の状況によっては、事業所の入居スペースだけでなく、建物全体に対する工事が必要になる場合があります。
万が一、必要な工事が行えない場合、物件の再選定が必要となり、開業の大幅な遅れにつながる可能性があります。
そのため、物件の賃貸借契約を締結する前に、必ず消防署と協議し、必要な設備や器具、運用面の要件を確認しておきましょう。
6.建築基準法上の要件
就労継続支援B型事業所として使用する物件は、建築基準法で定められた要件を満たしている必要があります。
適法な物件でなければ、利用者の安全を確保できず、事業の運営にも支障をきたす可能性があります。
既存の物件を使用する場合は、建築当時に検査を受けたことを証明する「検査済証」があるかを確認し、基準を満たしているかを把握しましょう。万が一、検査済証が紛失している場合でも、特定行政庁に問い合わせることで検査履歴を確認できます。
また、「用途変更」が必要となるケースもあるため、事前に確認し、必要に応じて建築士へ業務を依頼することを検討しましょう。
就労継続支援B型事業の開業までの流れ
就労継続支援事業所を開業するには、いくつかの準備や手続きを進める必要があります。開業には6ヶ月から1年ほどの期間がかかるため早め早めの行動が大切です。
開業までの期間が長引くと、初期費用が増加する可能性もあるため、申請のタイミングや順序をしっかりと把握し、慎重に準備を進めていきましょう。
1.情報収集・管轄の自治体と相談する
物件の取得やスタッフの採用後に自治体に相談しても、基準を満たしていなければ最初からやり直しになってしまいます。 そのならないために、まずは情報収集・自治体への相談が大切です。
開業手続きやローカルルールは、指定権者(障がい福祉サービスの許認可を出す行政機関)ごとに異なるため、指定権者のWEBサイトなどを通じて必要書類や手続きの流れを調べましょう。
十分に情報収集をおこなえたら、指定権者の窓口に相談に行きます。
この際に、事前に電話して相談に行きたい旨を伝えておくとスムーズです。
2.事業計画書の作成
事業計画書は、開業の目的や必要な資金、予想される収益などを記載した計画書で、行政や融資を担当する金融機関が、事業が無理なく運営できるかどうかを判断する際に使用されます。
現実味のない、思いつきで作成したような事業計画書では、行政が開業を認めないことが多く、仮に開業できたとしても、経営が難しくなる可能性が高くなります。
どんな事業所にするかを明確にし、サービスや生産活動、収益などしっかりとプランニングしましょう。
また、事業計画書を作成する段階で、法人設立や事業の内容、資金調達の相談もこのタイミングで行います。
この事業計画書は、指定権者からの許可を得るためだけでなく、金融機関からの融資を受ける際にも重要な役割を果たすため、できる限り綿密に作成しましょう。
3.必要な書類を準備する
次に準備するのが、申請に必要な書類です。種類が豊富にあるため、必ず抜けや漏れがないようにチェックしておきましょう。主な書類は下記のとおりです。
- 事業計画書
- 事業所の平面図・内外の写真
- 指定申請書
- 指定に係る記載事項
- 組織体制図
- 役員名簿
- 管理者・サービス管理責任者の経歴書
- スタッフの資格証明書
4.申請書類を提出する
事前協議や事前相談を経た後は、いよいよ申請です。準備した書類を指定権者の窓口に申請します。
指定日(開業日)が毎月1日とされているケースが多いですが、指定権者によって異なるため、あらかじめスケジュールを確認しておきましょう。
5.実地確認を受ける
必要書類を提出後、指定権者は書類に不備がないかを確認しますが、場合によっては修正や追加書類の提出を求められることがあります。そのため、余裕を持ってスケジュールを立てましょう。
書類に問題がなければ、担当者が開業予定の就労継続支援B型事業所の物件を訪問し、以下の点を実地確認します。
- 提出された書類と内容に相違がないか
- 必要な要件を満たす人材が採用されているか
- 物件や設備に問題がないか
- B型事業所としてサービス提供に問題がないかなど
6.指定書を受け取る
ここまでの流れでとくに問題がなければ、就労継続支援B型事業所として指定を受けて開業することができます。 申請書類の受理や実地確認から早くても1ヶ月から2ヶ月後に指定(開業)となります。
基本的に特別な理由がない限りは毎月1日付での指定となりますが、指定権者により異なる可能性があるため事前にスケジュールを確認しておくと良いでしょう。
開業するための相談先
就労継続支援B型の開業申請にあたり、相談先を見つけることは重要です。
効率よく進めるためには専門家のサポートを受けることが重要です。そのため、信頼できる相談先を事前に確保しておくことが望ましいでしょう。
行政
就労継続支援B型の指定権者は、事業所が所在する場所によって異なります。
地域ごとにローカルルールがある場合もあるため、開業予定の地域が決まったら、指定権者を確認し、あらかじめWEBサイトなどで情報収集をして早めに相談するとよいでしょう。
行政書士
自力での申請書類作成が難しい場合、障がい福祉サービスを専門とする行政書士は許認可申請に必要な書類の作成代行や申請サポートをしてくれます。
ただし行政によっては行政書士の完全な書類作成代行を認めていない場合があるため、あらかじめ行政に相談したうえで判断しましょう。
コンサルタント
事業コンセプトの制定やエリア選定や物件探しなどのサポートを幅広く対応してもらえます。
就労継続支援B型事業所の開業や経営まで全般的に不安がある場合は、福祉事業の開業コンサルタントに相談すると良いでしょう。
コンサルタントによって得意分野や支払う報酬は異なるので、相談したい内容と予算に合ったところを選ぶことがポイントです。
就労継続支援B型 開業支援サービスはじめます!
B型事業所立ち上げでコンサルタントをお探しの方必見!
2020年からスタートし、合計30社以上の障がい者グループホームの立ち上げ支援を行ってきた福祉経営サポートセンターで
このたび新たに『就労継続支援B型事業所立ち上げ支援サービス』を開始します!
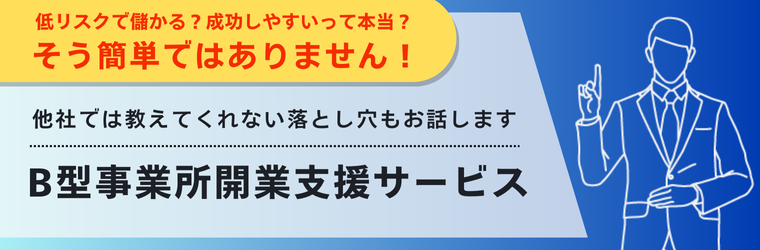
「最短◯ヶ月で黒字化可能!」
「申請などの面倒な手続きを代行します!」
「ゲームをするだけで工賃が貰えるので利用者さんが集まりやすく定着率が高い!」
といった『簡単にはじめられて儲かる』ような内容を謳う立ち上げ支援団体が近年増え始めています。
B型事業所の運営は、基盤となるビジネスをしっかり作り込み長期的に安定した運営を行うこと、
その上で利用者様が自立に向かって働けるよう意味のあるお仕事を提供することが非常に重要です。
企業側が利益を生むためだけに意味のないお仕事で利用者様を囲い込むことは
利用者様の自立に繋がらず障害福祉サービスとの在り方として全く本質的ではありません。
きちんとしたサービス提供を目指している事業者様がこのような団体の支援を受け後悔することのないよう
弊社では運営側の視点で地に足のついたB型事業所の立ち上げ支援を行います。
正式なサービススタートは2025年中を予定しておりますが、支援開始前に弊社が運営するB型事業所見学会を開催いたします!
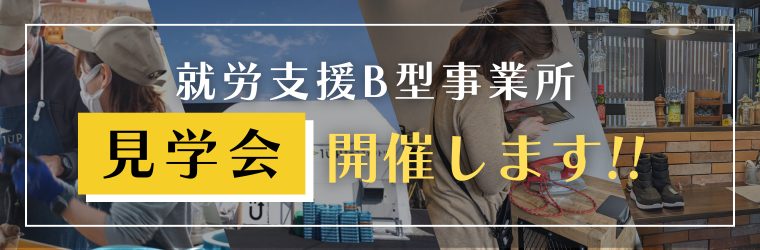
B型事業所ってどんなところ?まずは実際に見てみるのが一番早いです!わからないこと、現地でしっかりご質問にお答えします。
詳細はこちらから!